仙台市 宮城野区 しらとり歯科医院です。「奥歯を失うと太りやすくなる」、奥歯を失うと思いの寄らないハプニングが起こります。身近な話から、ブリッジ、入れ歯、インプラント治療の必要性についてお伝えしたいと思います。
1.インプラント手術の実際から注意点まで徹底解説
・インプラント手術の実際
・知らないでは済まされない失った歯が招く問題
・インプラントと噛む力について
・術後の注意点
・事前によく聞かれる質問

【知らないでは済まされない失った歯が招く問題】
・総入れ歯への道:1本の歯が招く負の連鎖
・歯のヒビ?:歯にかかる力とそのダメージ
・骨の吸収と歯並びの変化:歯を失ったまま放置するリスク
・歯を失うことの影響と治療の選択肢
・奥歯がなくなると太りやすい?

早食いと奥歯の喪失が招く「肥満リスク」:現代人の食と健康
「早食いも芸のうち」ということわざを聞いたことがあると思います。食事を早く済ませることも才能や特技の一つとみなせるといった意味で使われていますが、元々は「早飯も芸のうち」といって、時間に制約のある職業(職人、武士、奉公人など)の方が食事を早く済ませたことに由来するそうです。
ここに加えて欲しい知識があります。実は「奥歯がなくなると太りやすい」ということです。どちらも噛む回数や食事時間に関係する話ですが、その理由をもう少し詳しくお話しします。

ゼリー飲料のキャッチコピー「忙しい朝に、10秒チャージ」。コンビニの軽食やファストフードのハンバーガーを流し込み、次の仕事に駆けつける、忙しい現代人にとってタイムパフォーマンスは大切だと思います。早食いが「芸のうち」と言われると聞こえは良いのかもしれませんが、時間を優先し過ぎると、からだにとってはものすごい負担になります。仮に奥歯を失ったとして、インプラント、入れ歯、ブリッジ治療を行わないと、傾向として食事をほとんど噛まずに胃に流し込んでしまい、消化不良になって、からだに負担をかけます。
現代人が噛まなくなった理由:失われた咀嚼回数と食文化の変化
日本咀嚼学会の理事長であった齋藤滋先生の研究によると、現代人の咀暗回数はパン、スープ、ハンバーグ、ポテトサラダの洋食の場合で一食当たり約620回、昔の食事を復元したもので咀嚼回数を比較すると、時代を遡るごとに咀嚼回数が上昇していることがわかりました。
江戸時代は1500回程度と現代の二倍、鎌倉時代では約2600回、弥生時代にまで遡ると4000回も噛んでいたことになるそうです。弥生時代の主な献立は、玄米、魚の干物、ノビル、くるみなどで、令和7年と比べ満足いくものかは置いといて、ただ言えることは、現代人は柔らかいものを食べる傾向にあり、噛む回数が激減しているということです。限られた時間の中で効率的に、簡単に済ますることのできる食べ物を選ぶ。そういった選択一つ一つが噛む回数の変化に影響をを与えています。

奥歯の喪失と脳のメカニズム:食欲と肥満の知られざる関係
もっと具体的に奥歯がない状態では、体内でどのようなことが起こっているのでしょうか。少し視点を変えて、からだの反応からみた奥歯を失う危険性についてお話しします。
食欲について、日常的に「甘いものは別腹」、「満腹中枢」と言ったりしますが、お腹の中だけではなく食事中は脳内で確変イベントが起こります。
「別腹」とは、「満腹の状態でも甘いデザートは別のお腹に入ってしまう」といったニュアンスだと思いますが、これは感覚的な話ではなく、実際に科学的な根拠があります。
科学誌Scienceに2025年、ねずみを使った研究・特集が掲載されました。脳には甘いものを受け入れる仕組み(神経回路)があり、お腹が一杯の状況でもデザートを欲しがってしまうといった内容です。不思議なもので甘いものを食べると「報酬系」といって脳内で快楽物質が生まれ、食欲が高まり、消化が促され、お腹の中で「別腹」が出来上がると言われています。
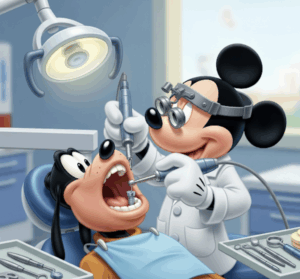
次回に続く